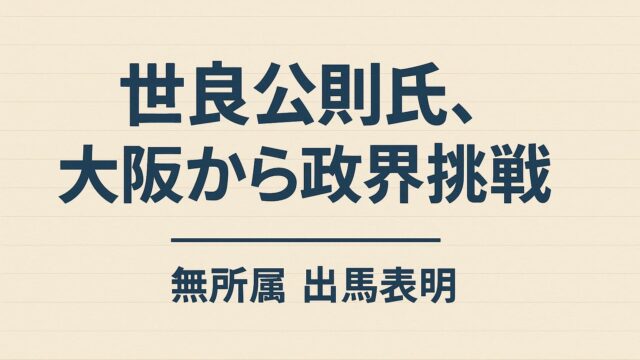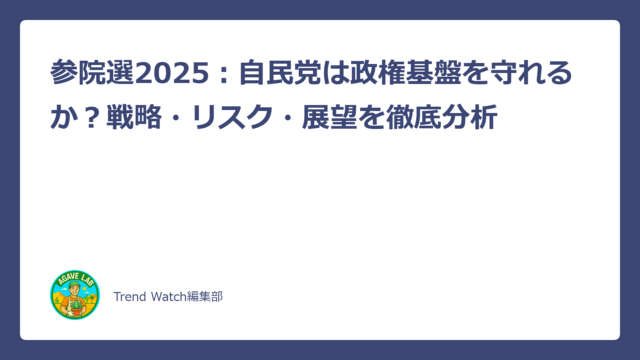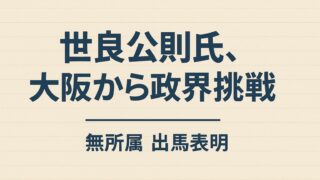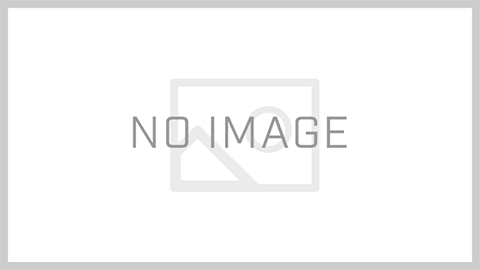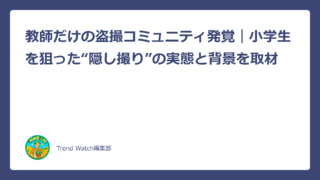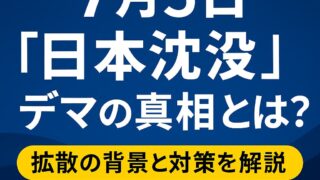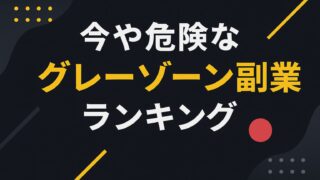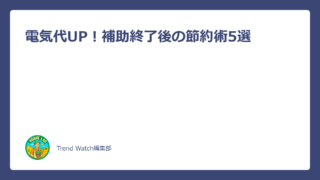2025年7月1日、石破茂首相は政府の関係閣僚会議で、今年産からのコメ増産を正式に表明しました。
これは食料自給率の向上や米価の安定化を目指すもので、新たなコメ政策への転換として注目されています。
しかし、農業の現場からは、こうした政策に対して戸惑いや不安の声も少なくありません。
この記事では、政策の要点と現場の課題、ネットの反応をもとに最新動向を整理します。
石破首相「コメ増産」の背景と狙い
政府はこれまで、需要に応じて米の作付けを調整する政策を取ってきました。
しかし近年、天候不順や世界情勢による物価高騰、そして食料安保への関心の高まりから、コメの安定供給を重視する動きが強まっています。
こうした中で石破首相は、「不安なく増産に取り組める新たなコメ政策に転換する」と明言しました。
つまり、これまでの需給調整から「生産拡大」へ大きく舵を切る内容です。
また、政府は備蓄米の確保や価格安定策も併せて進め、農家の経営リスクを減らすことを目指しています。
現場の農家はどう受け止めた?
一方で、今回の政策についてネットでは小規模農家の不安が多数見られました。
このような声は、政府の思惑と現場とのギャップを明確にしています。
さらに、動物被害や気候変動のリスクも深刻化しています。
つまり、物理的な被害対策も十分でない中、増産の負担だけが重くのしかかる構図が見えてきます。
増産=コスト増?機械の高騰と苦悩
さらに、農業機械の高額化も農家の悩みの一つです。
特にコンバインなど大型機は、2000万円以上するケースも珍しくありません。
このように、面積を増やすためには土地代だけでなく、機械更新費も必要になります。
加えて、機械の寿命は平均15年ほど。定期的な更新が欠かせません。
そのため、政府が機械導入やメンテナンス支援にどこまで踏み込めるかが今後の鍵となりそうです。
「精米前販売」で食品ロス削減も
また、増産と並行して精米流通の見直しを求める声もあります。
たしかに、精米後の米は劣化が早く、長期保存が難しいとされています。
一方、精米前の米であれば、虫害や品質管理に気をつければ長持ちします。
とくに地方ではコイン精米機が身近にあるため、自分で精米できる環境が整っている地域も多いです。
そのため、消費者の選択肢として「精米前販売」の検討も求められています。
現場の声を反映した政策を
ここまで見てきたように、今回の政策にはさまざまな課題が伴います。
そのため、机上の政策だけでなく、現場の実態を反映した支援が不可欠です。
今後の焦点は、以下の3点に集まると考えられます。
- 農業機械・資材費用への具体的補助策
- 小規模農家への継続的支援と担い手育成
- 精米・流通まで含めた総合的な改革
加えて、農業現場では高齢化や人手不足も深刻です。
こうした問題も含め、次世代への橋渡しとなる農政改革が求められています。
よくある質問(FAQ)
Q1:なぜ今、増産なのですか?
A:物価上昇や天候不順で米の供給安定が課題となり、備蓄強化のために増産が必要と判断されました。
Q2:小規模農家にも恩恵はありますか?
A:支援の対象には含まれますが、現場からは費用や労力面での懸念の声も上がっています。
Q3:精米前販売は本当に実現可能?
A:保存性の高さなどから注目されていますが、実現には制度や流通の見直しが必要です。